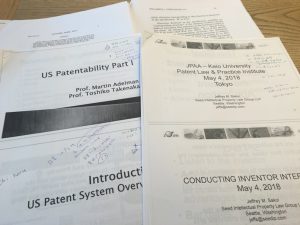ログイン方法を忘れるくらい久しぶりのブログ更新です…。
Golden Weekに開催された、弁理士会・慶應ロースクール共催のセミナーに参加しました。
『アメリカ特許法とその手続』 (Donald Chisum) の訳者として憧れていたCASRIPの竹中俊子先生が、最近、慶応ロースクールでも教鞭を執られていることは知っていましたが、ロースクールに通うのはハードルが高すぎるなぁと諦め・羨望の想いでいたので、竹中先生の講義を受けられるこのセミナーにはどうしても参加したいと思っていました。抽選で一度落選しましたが、キャンセル待ちを熱望したら2回目の抽選で入れてもらえました 😀 。粘ってみるものですね。
参加者は、事務所や企業の弁護士・弁理士の方々をはじめ、特許庁の審査官、知財高裁の裁判官、慶応ロースクールや神戸大学の学生さん等、錚々たる方々でした。さらに最終日には、高部眞規子知財高裁所長もゲストとしていらっしゃっていました!
フリーで翻訳をはじめて早10年…特許実務から完全に離れてしまっているlonerの私にとっては、知らないことばかりで、新しいことをたくさん教わることができ、また、非常にレベルの高い参加者の皆様に大変刺激を受けました。(皆様、質問のレベルが高いだけでなく、英語もものすごくお上手で、翻訳者を名乗るのが恥ずかしいくらいでした…。)
セミナーの内容は、最近の判例等からみる米国特許実務、USPTOにおける手続き(IPR, CBM, PGR等の違いや裁判との関係)、裁判手続き、ITC手続き等々、広範にわたりました。
翻訳に直結する話題はさほど多くなかったのですが、翻訳実務でも役に立ちそうな情報をいくつかご紹介します。
(1)Means-plus-function (MPF) をどう訳すか。
ソフトウェア関連発明などにおいて機能的表現をどのように訳すかというのは昔から議論のあるところだと思います。Williamson v Citrix Online (2015年CAFC en banc判決)を受けて、単にmeans以外の用語(例えば、moduleやdeviceやunit)を使って機能的クレームを記載しても、構造的文言がクレームされていない場合は112条(f)項でMPFと判断されてしまう可能性が高く、その場合、明細書に、そのエレメントに相当する構造だとか、機能を実現するのに必要なアルゴリズムやフローが開示されていないと、クレームが不明確であるとして拒絶・無効の対象となる、とのことでした。結局、MPFエレメントをどう訳すかという問題ではなく、基礎となった和文明細書の中身が問題となるので、翻訳の段階では対処のしようがないのかな、と思ってしまいました。こういうトレンドがあることを知り、MPFエレメントに対応する開示をきちんと丁寧に翻訳する点には気をつけようと思いました。 (あ、もしかしたら、MPEP2181に構造的文言として例示されているcircuitとかを使えば112条(f)項の適用を避けられるのか…?聞きそびれました。)
(2)101条拒絶の対処方法。
Mayo判決、Myriad判決からのAlice判決を受けて、ソフトウェア関連発明も101条のeligibility (発明該当性) の拒絶を受けることが非常に多くなっているとのことで、その対処方法を教わりました。Alice判決を受けて、101条の該当性はtwo-part test (Step 1: Not directed to an abstract idea; Step 2: Significantly more) で判断されることとなりました。日本のクライアントさんのOAレターや意見書を英訳する場合には、このあたりの事情を理解して、MPEPや判例で使用されている用語を効果的に使いながら英訳するといいのかなと思いました。
例えば、Alice判決後に101条の「eligibilityあり」と判断されたDDR Holdings v Hotels.com事件で使われた表現 (Step 1: “the claimed solution is necessarily rooted in computer technology in order to overcome a problem specifically arising in the realm of computer networks.” とか Step 2: “the claims recite an invention that is not merely the routine or conventional use of the Internet.”) が非常に効果的なのではないかと思いました。
(3)「本発明」という語をどう訳すか。
米国の訴訟などで限定解釈の恐れがある「本発明」という用語をそのままpresent inventionと訳すべきか、present disclosure等と訳すべきかという問題も昔から議論されているところですが、米国訴訟では、present disclosureと訳したとしても、第1国出願(日本出願)の開示にまで遡って争われてしまい、日本語明細書に「本発明」と書いてあること自体をつっつかれてしまうので、結局は翻訳時にどう訳すかという問題よりも、おおもとの日本出願の内容が問題となってしまう、との話でした。 (判例があるとのことでしたら、事件名を聞きそびれてしまいました。) なので、出願人としては、その発明の主たるマーケットはどこなのかをしっかり検討して、米国がマーケットなら、米国に第1国出願をすべき、とのことでした。
(4)ITC関連の用語は独特。
ITCの事件は年に60件くらいしかないそうなので、まず翻訳で携わることは (私は) ないと思うのですが、ITCでは、District Courtなどの通常の裁判で使われる用語とちょっと違うよ、という話がありました。
裁判所 → ITC
Plaintiff → Complainant
Defendant → Respondent
District Court Judge → Administrative Law Judge
Injunctive Remedies → Exclusion Order
Investigative Attorney from Office of Unfair Import Investigations (OUII) という第三の当事者が関わってくる点も大きく違うとのことでした。
(5)そのほか。
そのほか、2018年4月24日に判決が出たばかりのOil States事件についてもお話がありました。この事件では「いったん特許として与えられた私権を、行政庁がIPR (付与後のレビュー) で無効とすることは憲法違反なのではないか?」という点が争われていたようですが、結局は、IPRは合憲だと判断されたようです。恥ずかしながら、特許無効が違憲だなんて考えたこともなかったので、かなり新鮮でした… 😯